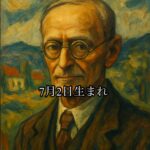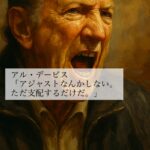【はじまり】
「無難なことからではなく、
正しいことから始めよ。」
「知性のはじまりの最初の兆候は、
死にたいと願うことだ。」
【道】
「わたしは自由です。
だから道に迷ったのです。」
「真の道は一本の綱の上に通じている。
その綱は空中に張られているのではなく、
地面のすぐ上に張ってある。
渡って歩くためよりは、
つまずかせるためのものであるらしい。」
「人が通ったところに、道は出来る。」
【悪】
「悪は善のことを知っている。
しかし善は悪のことを知らない。」
「悪の最も効果的な誘惑手段の一つは
闘争への誘いだ。」
「人間には他のあらゆる罪悪が
そこから出てくる二つの主な罪悪がある。
すなわち短気と怠惰。」
【書物】
「書物は我々のうちなる
凍った海のための斧なのだ。」
「自分を傷つけたり、
刺したりするような本だけを読むべきだと思う。」
「多くの書物には、
自分自身の城内の未知の広間を開く、
鍵のような働きがある。」
【見出される者】
「探し求める者は
見つけることができないが、
探し求めない者は見出される。」
「鳥籠が鳥を探しに出かけていった。」
【その他】
「人間を吟味せよ。
疑う者には疑わせ、
信じる者には信じさせよ。」
「あなたと世の中との戦いなら、
世の中のほうに賭けなさい。」
「あなたの口のなかに食べ物がある限り、
すべての問題はとりあえず解決されたのです。」
「なぜ、人間は
血のつまったただの袋では
ないのだろうか。」
フランツ・カフカはプラハ出身の作家であり、後の不条理文学や実存主義文学を先取りした先駆的な存在です 。サルトル、カミュ、ベケット、そしてジム・モリスンといった、20世紀を代表する思想家やアーティストたちにも多大な影響を与え、彼らの作品や哲学の基礎には、カフカが描き出した理不尽で不可解な世界に投げ出された人間の姿が色濃く反映されています。
彼の作品は、人間が人生の意味を問い求めても世界は答えず沈黙するという構造――つまり不条理 ――の中に投げ出された個人の苦悩を描いています。その世界では、理解不能な状況や理由なき裁き、目的の見いだせない制度の中で 、人はただ立ち尽くすしかありません。その理不尽さと孤独感の“現実味”は、時代を超えて多くの読者に共鳴を呼び起こしています。
代表作『変身』『審判』『城』では、不可解な状況に巻き込まれ翻弄される主人公たちを通じて、意味の見えない世界に生きる人間の苦悩が克明に描き出されています 。
ただし、カフカの思想全体が単純に虚無や無意味一色だったわけではないという見解もあります。例えばサルトルは、カフカの作品を不条理そのものではなく「幻想文学(le fantastique)」として読み解き、不条理の解釈だけに回収できない含意があると論じました。
しかし一般的には、カフカの作品世界は「究極的な意味や救済が提示されない」という点で不条理的であるとの解釈が広く支持されています 。
カフカの残した短い箴言の数々にも現代人の不安や葛藤が凝縮されており、その簡潔な言葉は今なお読む者の心を深く揺さぶり続けています。