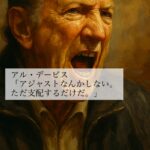コクトー
「『愛する』という動詞の活用は難しい。
過去形は単純ではなく、現在形はただの直説法、
そして未来形は常に条件法である。」
(フランス語での愛)
フェデリコ・フェリーニ
「言語が違えば、
人生の見え方も変わる。」
コクトー
「歴史とは、幻想へと変わる真実であり、
神話とは、現実となる幻想である。」
ジョーゼフ・キャンベル
「神話は、歴史よりもはるかに重要で、
はるかに真実である。
歴史なんて所詮ジャーナリズムにすぎない
――そして、それがどれほど信頼できるかは、
あなたもご存じのとおりだ。」
コクトー
「運を信じなければならない。
さもなくば、なぜ嫌いな人間が
成功するのか説明がつかないだろう?」
マイケル・サンデル
「自らの境遇が
偶然に左右されているという感覚を自覚すれば、
ある種の“謙虚さ”が生まれる。
ーーーこの謙虚さこそが、私たちを分断する
“冷酷な成功の倫理”から脱却する第一歩となる。
そしてそれは、実力主義という名の専制を超え、
もっと寛容で寛大な公共のあり方へと
私たちを導くものなのだ。」
ジャン・コクトーはフランスの芸術家で、詩人・劇作家・映画監督・画家として活躍し、「芸術のデパート」とも称された人物です。
『恐るべき子供たち』『人間の声』『大胯びらき』、詩集『アラジンのランプ』などを残し、映画では『美女と野獣』『詩人の血』、バレエ『パラード』ではサティ(音楽)、ピカソ(美術)と共演するなど、多彩な才能を発揮しました。
ダダやシュルレアリスムと響き合う要素はありましたが、コクトー自身はこれらの運動には加わらず、特にアンドレ・ブルトンらとは対立もしています。
詩人であることを何より望んだ彼の言葉は、現実の背後にある“見えざる真実”を照らし出そうとします。
「『愛する』という動詞の活用は難しい」という名言には、フランス語の文法から愛の不安定さを見抜く鋭さがあります。――では、日本語の「愛する」はどうでしょう?
また、「運を信じなければ、嫌いな人の成功を説明できない」という皮肉には、現代社会への批評精神がにじみます。
実際、アメリカでは「努力=成功」の信念が強い一方、ヨーロッパでは成功を「制度や偶然」の結果と見る傾向もあります。
コクトーの言葉は、そうした価値観の違いを鋭く捉え、現実を受け入れるための“詩的な論理”として、いまを生きる私たちにも問いかけてきます。