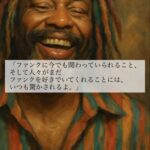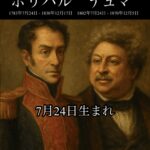「人生とは、
常に次へ次へと続く生成である。
課題の後にはまた課題があり、
どこにも終止符はない。」
「人の人生は、前半と後半に分かれている。
前半では後半を待ち望み、
後半では前半を懐かしむ。
経験とは、
望まぬことを経験することによって成立する。」
「人間界のどこにでも、
美しいものと醜いものは混じり合っている。
誰もが、自分の中に
“テルシーテース”(※)を抱えているのだ。」
(※ テルシーテース=ホメロス『イリアス』に
登場する醜悪で卑劣な男)
「感謝は、後の世の美徳である。」
(※「後の世」とは、恩を受けた当事者ではなく、
次の世代や後継者が感謝するという意味)
「人間の文化がまだ芽のままで
発展していない粗野な時代は、
決して“醜い”のではない。
本当に醜いのは、かつての教養の残骸が
腐敗しているような、気力を失った時代だ。」
「感情の奔流の中でも、理性が自分の根拠を見失わず、
揺るぎない現在的な働きを続ける。
それが“精神の現在”である。
これなしには、『冷静さ』や『沈着さ』はあり得ない。
精神の現在がなければ、
思考はすべて不安と混乱に陥るだろう。」
「唯一、自由の行為と証と呼べる心の変化は、
外側で起きるのではなく、
人格の最も内奥で起きる。
それは、利己心に動かされる
意志の方向を変えることであり、“転換”である。
自らの中に深く入り込み、
そこで自然な性格を制御することができなければ、
その人は本当の自由を
使いこなしているとは言えない。」
クーノ・フィッシャーは、ドイツ観念論を中心とした哲学史の大解説者であり、哲学の「流れ」と「つながり」を明快に体系化した思想家です。プロイセン王国の都市グーラウ(現ポーランド領グラ)近郊で生まれました。
彼は、唯物論やショーペンハウアーが流行する時代にあっても、哲学を学ぶならカントやヘーゲル、さらにはその源流であるデカルトやスピノザを無視してはならないと考え、1852年から『近代哲学史』全10巻(11冊)を刊行しました。このシリーズでは、デカルト、スピノザ、ライプニッツ、カント(2巻)、フィヒテ、シェリング、ヘーゲル(2巻)、ショーペンハウアー、ベーコンを順に取り上げ、それぞれの生涯と思想を文学的かつ明晰に再構成し、当時「哲学を学ぶならフィッシャーから始めよ」とまで言われるほど広く読まれました。彼の仕事は、単なる哲学史の解説にとどまらず、カントやヘーゲルの再評価を促し、時代の風潮に流されずに哲学の原点回帰を促すものであり、哲学の「精神」を次世代に伝える重要な役割を果たしました。